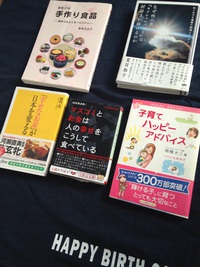2013年08月16日
昔の日本人と今の日本人


子どもが一歳を過ぎてだいぶ歩き回るようになってきた。
今の生活のの中で最優先順位は子供の教育なのだけれども、改めて子どもたちに教えるべきことを考えた時に自分が何も知らない事に気がつく。
経済優先の競争社会の中で育ったうちらの世代は生活のすべを全部お金を稼いで物を買うということでしか生活できないようになってしまった。
その欲望を限りなく煽られ経済競争の泥沼にはまり込んでしまったのである。
ただ、唯一の救いは「自分たちは何も知らない」ということを知ることができた世代であることである。
そのような視点で物事を見てみるとやはり江戸時代の文化に現代人がはまり込んでいる泥沼からの脱出方法があるのではないかということに気がつく。
次の世代には自分たちのような生き方は勧めたくないし、そんな生活はもう地球のエコシステム限界に達してできなくなる。
今になってあわてて山仕事や、自然農、などを経済競争の隙間に学んでいるところである。
それを次の世代の教育の基本にして昔の日本人に負けないかっこいい日本人になってもらいたいと思う。
カッコいい江戸時代の日本人
http://quasimoto.exblog.jp/18119707/
江戸の市民生活の素晴らしさのエピソードとして完全リサイクル有機農法を紹介します。
現代の都会生活でもアパートやマンションの集合住宅が多いように、江戸でも「長屋」がありました。大家が50両払って代官から営業権を購入します。
家賃はいりません。さらに「老人」や「病人」が入居人として歓迎されたと言います。住人の仕事は「用をたす」ことだったからです。
ちなみに、当時、上下水道が完備していたのも、世界で江戸だけです。その下水道に、「トイレ」の排泄物を流すことは厳禁です。それだけ、衛生管理観念も進んでいました。下水道にトイレの排泄物を流すようになったのは、「文明開化」した明治維新以降なのです。欧米化が日本文明を劣化させた一つの例証です。
長屋で溜められた「うんち」は、郊外の農家が買い取りに来ます。その売り上げが、現代価格で年1000万円ほどになったようです。つまり、それだけ現金を出せた農民も豊かだったのです。
農家では、それを肥だめで微生物利用による完全有機肥料として活用しました。世界で初の完全有機リサイクル農法だったわけです。老人や病人は、消化力が落ちているので、排泄物の中に「有効成分」が多く、貴重な存在として大事にされたわけです。正月などには、わが子のように住人に大家さんがお餅などを配ったのです。
このような市民のパラダイス国家を運営していたのが、侍たちです。彼らは、武道に励みながら、市民のために誠実にこの国を切り盛りしていました。なにせ300諸藩も、市民も一切江戸幕府に税金を納める必要はありませんでした。
完璧な地方自治で、経済的にも独立し、幕府も各藩も、自己責任でキチンと運営しなければならなかったのです。組織・制度上からも為政者たちが、エゴの「利権」に走ることなど出来なかったのです。
しかも彼らは、生まれたときから15才で元服するまで、「武士としてのこころ、躾、言葉、文、理」を、市民以上に藩校などで、専門の講師たちに徹底して訓育されました。優秀なものは、身分にかかわらず、他の藩校や幕府の昌平校などに藩費で留学もできました。この中には、商人や農民の優秀な子どもも選抜されていました。武士になれたのです。このように生まれたときから高度の人間教育を受け、いざというときは命さえ惜しまない世界最高の利他を体現する為政者、それが江戸時代の侍=武士だったのです。
先ずはハラを意識した生活が必要だと思う。
頭からハラへ意識を向ける。頭からハラに意識をかえると自我が弱まり自然との一体感が強まり思考も行動もより自然に近づいてくる感じがします。
中でも丹田を自然に鍛えられる遊びは5S(サーフ、スノー、スキー、スケート、スラックライン)
やっている人たちは自然派が多いです。
頭より丹田を意識しているからではないかと思います。
『ハラを失くした日本人』より抜粋
「ハラが立つ」から「頭にくる」へ
T 身体意識言語の盛衰については、おもしろい話があります。覚えておいでかどうかわかりませんが、昭和30年代も末の頃だと思いますが、「肝」や「腸」が使われなくなり、いよいよ衰退の波が「肚」にまでおよびつつあったちょうどその頃、勢力を拡大した言葉がありました。その時代までは「怒る」ということを身体意識言語を使って「肚(腹)立つ」という言い方が普通だったのですが、ちょうどその頃、別の身体意識を使う言葉がこれに取って替わり始めたのです。
ー・・・それはもしかすると「頭にくる」ではありませんか?
T 正解です。「怒る」という情動をそれまでの日本人は身体の中の"腹部"の身体意識"肚"をもって成立させ認識していたわけです。
「肚(腹)」を使って心持ちや情動を表す言い方は大変古く、例えば平安時代の大鏡にすでに「おぼしき事いはぬはげにぞ腹ふくるる心地ぞしける」とあります。少し時代は下がりますが、平家物語にも「腹がゐる」という言い方が見られ、平安時代には日本人は「肚(腹)」を使って情動を成立させ認識し、あるいは制御していたことが分かるのです。
ー「腹にくる」というのは「怒る」という意味なのでしょうが、「腹がゐる」というのはどういう意味なのですか?
T「怒りがおさまる」とか「気がすむ」といった意味で使われているようです。
ーそれだけの伝統、ザッと見積っても一千年間日本人を支えてきた言葉が、昭和30年以後の僅かな期間に失われていってしまったわけですね…。
T 今の若い人たちに「肚」を使った言い回しを聞かせると、一致して「おじいちゃん、おばあちゃんが使っていた言葉」という返事が返ってきます。もちろん彼らの両親の世代、つまり戦中生まれの人々も、こうした言葉を幼年から青年期までは多用していたのでしょうが、彼らの子供たちつまり今の若者たちが少年期をむかえる頃にはほとんど使わなくなっていた、ということなのでしょう。
ー最近のメンタルトレーニングの中に"腹部"を意識させて呼吸をコントロールしたり"腹部"に手を置いて意識をコントロールしたりするメソッドがありますが、日本人はすでに一千年も前から、当然至極の生活のまっただ中でこうしたメンタルコントロールを行なっていた、あるいは少なくともそういう方向性を持っていた、ということが言えるわけですね…。
T 「頭にくる/来ない」と言葉で情動を捉えると、たとえ「頭に来ない」場合でも身体意識は"頭部"に強く定位されます。これを運動科学では言葉による意識のサモン(支持する、とくに強く指し示す)と呼んでいますが、言葉にはこのように身体意識の志向性や定位、強化を自動的にコントロールしてしまう力、つまりサモン効果があるわけです。
ですから「頭」という語を使って情動表現をしていると、人は興奮/冷製にかかわらずあらゆる場合に、自分の身体の中心感覚を"頭部"に置いた状態、つまり"頭デッカチ"の極めて問題のある状態に身を置いて生き続けることになるわけです。
ー…ということは、「肚」か「頭」のどちらかを使うだけで、メンタルコントロールにも違いが生じてしまう、ということなのですね。するとやはり日本人はすでに平安時代の段階から現在最先端のメンタルコントロール法を、日常茶飯の中で、全民族的一般性において行なっていた…ということになるわけですね。
T そうした日本民族一千年(以上)の価値ある伝統が、よりにもよって東京オリンピックを境に失われていこうとは…何という皮肉なできごとではないでしょうか。
ー 考えてみますと今の話は「怒り」の情動を表す「腹(腹)」一つに留まらない話しなわけですね…。「肚を括る」とか「肚ができている」などの「肚」や、さらに「身」「筋」「肝」「腰」等々のすべてについても、大なり小なり同じように見られる話なわけですよね…これは大変な問題ではないですか⁉
T そうでしょう…まさに言われる通り、これは日本文化史上とてつもない問題であると、私は思っているのです。
武術・武道も、能・歌舞伎・文楽・邦楽・茶・華も、そして礼法も、一切の武芸ー技芸が、「気が通い」「見にしみる」身体意識を「身をもって知る」認識力を根底とし、「肚を括り」「気の入った」生き様の中から鍛え抜かれた「足腰」に支えられたところの「心気息一致」の「筋金入りの技」によってのみ、創造され、伝承され、発展せられてきたことは紛れもない事実なのです。
いや実はその関係する領域は、こんなものには留まりません。建築も工芸も料理も、そして日本しきの超集約的農業も、林業も、さらには伝統的な健康法ー治療体系もが、「身」と「気」と「筋」と「肝」と「腸」と「肚」と「腰」によって格別に高められ深められた身体意識なしには、この世に存在することはなかったのですから。
コーナー『ディレクト・システム』
ディレクト・システム理論は人類が身体運動を含むあらゆる活動において能力を最高度に発揮するため、長い歴史の過程で無意識のうちに生み出してきた方法を、筆者か科学的・一般的に解明した理論である。
ここでは身体運動に焦点を絞って簡単な解説を行う。まず具体例をあげて説明しよう。
野球やテニスの指導者がしばしば「手ではなくて腰でボールを打て!」という言い方をする。この場合その「腰」は単に解剖学的な腰を意味するものでははない。物理的に考えてもボールを打つのは、腰でも手でもなく、バットやラケットである。しかし、「腰でボールを打つ」という言い回しを常時使用していると、上手く打てた時には、まさに運動する身体(=主観的身体)の中を、"下半身"から発生した「腰」という名のエネルギーの塊が体幹を通って胸から肩、肩から腕を通ってバットの芯へと移動していくのが感じられるようになるのである。この時の「腰」のように、目標とするパフォーマンスをいつでも実現できるようにするために、運動主体の認識に直接働きかける作用を持つものをてディレクターと呼び、ディレクターによって構成される「認識力ー制御体系」をディレクト・システムと呼んでいる。
剣道で使われる「正中線」、スキーやバレエの「センター」、ゴルフの「軸」、自転車やオートバイ競技の「ライン」、そして合気道や気功法の「気」等もディレクターの典型的な具体例である。
人間がある水準以上のレベルで行うためには、優れたディレクターによって構成される高度なディレクト・システムを見出だし、目的とする運動をすべてそのディレクト・システムによって押さえきれるよう日頃からトレーニングすることが必要である。人間の身体は無限に多様な変形が可能であり、それによって下界と多様な関係を結び、多様な運動を行うことが可能になっているわけであるが、一つの運動に高度に習熟するためにはそれがかえって障害となる。ディレクターおよびディレクト・システムは、多様な変動性を持った人間の運動に一つの明確な構造を作り、それによって同じ人間が精密機械にも勝る超常的運動を行うことも可能にするものである。
しかし、ディレクト・システムの威力はそれに留まらない。ディレクト・システム・トレーニングを行うと身体意識が活性化されるため、単にその運動に習熟するだけでなく、知覚・意識操作能力や独創性までもが開発される。こうした能力はあらゆる人間関係の成否を担うものであり、その影響は測りしれないものがある。
古来一毫の乱れも許さぬ剣捌きを体得して剣術家や、一寸の狂いもないスピンを演じたバレリーナが日常何気なく行う動作や仕種の中に言い知れぬ迫力や気品を感じさせたというのは、彼らが知らず知らずのうちに無上の「正中線」や「センター」
を己が身体の中に築き上げていたからである。
筆者か行った指導でも、「ディレクト・システムを用いてのピアノトレーニングに取り組んだら、スキーや料理が上達してしまった」「武道の技を磨くためには呼吸法でハラづくりをしていたらビジネスも上手くいくようになってしまった」「卓球でセンタートレーニングをやったら身体が美しくなり表情も輝いてきたと皆から言われた」…等々、その影響力を示す例は枚挙には暇がない。
「ディレクト・システムは人間の本質力を高めるものである」ことを示す証である。
(参考文献『鍛錬の方法ー世界最強をめざす人だけが読む本』等)
お米を作ろう
2016参議院議員選挙 自然循環型米作り
固定種野菜の苗のためのビニールハウス作り
母子手帳改正
信州の里山資本主義 のとゆ展とロケットストーブワークショップ
牛乳なし給食 試行へ 新潟・三条市 牛乳について考える
2016参議院議員選挙 自然循環型米作り
固定種野菜の苗のためのビニールハウス作り
母子手帳改正
信州の里山資本主義 のとゆ展とロケットストーブワークショップ
牛乳なし給食 試行へ 新潟・三条市 牛乳について考える