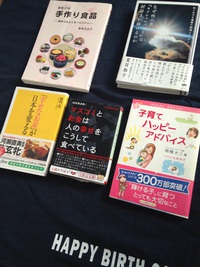2010年06月28日
神社とおもてなし



なんだか最近は神社ブーム。
パワースポットや癒やしの空間としても行くようですが、本来神社とは何をする場所だったのか?
おもしろい記事を見つけたのでご紹介します
ひと口に「神社」といっても、立派な社殿を持つ神社もあれば、横町裏のお稲荷さんや、オフィス街にひっそりたたずむ小さなほ祠もあります。それらは規模の大小はあっても、すべて神様の降臨する神聖な場所であり神様が祀られています。
神社とは、一言でいえば「神を祀る場所」のこと。ただし、なかには神様を祀る「本殿」のない神社もあります。たとえば、奈良県の大神神社、長野県では長谷神社(長谷寺敷地内にあります)は御神体が山そのものなので、神社にあるはずの本殿が存在しません。
しかし、じつはこの大神神社や長谷神社のスタイルのほうが、本来の神社の姿、原点ともいえるのです。
日本には「八百万の神」がいると言われるように、日本人は古くから森羅万象のなかに神性を認め、崇拝してきました。たとえば、『古事記』や『日本書紀』に登場する天照大神をはじめとする神々のほか、菅原道真のような実在の人物が神様になったケースもあるし、土地の守護神である産土神や氏神など、実に多彩な神様が存在します。ただし、神社という建物をつくり、そこに神々を祀るようになったのは、寺院を建設する仏教が伝来し、その影響を受けてからのことです。それ以前は、いまのような常設の建築物としての神社はほとんどなかったのです。祭事を行うときには、そのつど臨時の祭場を設け、ごちそうをつくってお供えし、神楽を演じたりして、神々をもてなしていました。
これが「祭り」の起こりで、神様を丁重にお迎えして、いっしょに楽しいひとときを過ごすことが、御利益につながるとされてきました。そして、祭りが終われば、その臨時の祭場は撤去されていたのです。つまり神社というのは、神を祀る場所というよりは、そもそもは「神をおもてなしするところ」だったのです
という記事でした
そうだったんだーて感じでした」
いまでも神社に米をお供えするのはそのなごりかもしれません
長谷寺、長谷神社は小さい時に遊んだ場所でもありますが
最近、気がついたことでした
あらためて行ってきたましたが拝殿の後は山そのものでした
よくわかりませんがなんかすごかったです
寺と神社がとなりどうしで並んでいて日本らしく寛容な感じでした
お米を作ろう
2016参議院議員選挙 自然循環型米作り
固定種野菜の苗のためのビニールハウス作り
母子手帳改正
信州の里山資本主義 のとゆ展とロケットストーブワークショップ
牛乳なし給食 試行へ 新潟・三条市 牛乳について考える
2016参議院議員選挙 自然循環型米作り
固定種野菜の苗のためのビニールハウス作り
母子手帳改正
信州の里山資本主義 のとゆ展とロケットストーブワークショップ
牛乳なし給食 試行へ 新潟・三条市 牛乳について考える
Posted by HAPPY BIRTH CAFE at 07:51│Comments(2)
│自然回帰
この記事へのコメント
どうも、カズです。ダライ・ラマには会えましたか?
Posted by インドのカズ at 2010年07月03日 23:28
インドのカズさんいつもありがとうございます
残念ながらダライ・ラマには会うことはできませんでした
遠くから見れただけでした
人がたくさん来ていました
残念ながらダライ・ラマには会うことはできませんでした
遠くから見れただけでした
人がたくさん来ていました
Posted by HAPPY BIRTH CAFE at 2010年07月08日 10:24